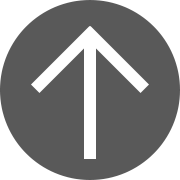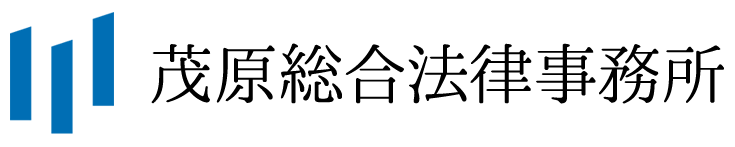お知らせ一覧
- 2023.07.19最近、父が亡くなったのですが、多額の借金していたことが分かりました。
- 2023.07.19遺産分割協議書とは何ですか。また、どのように作るのですか。
- 2023.07.20遺産分割はいつまでに終わらせる必要がありますか。
- 2023.07.20兄弟間で、遺産分割の話し合いがまとまりません。今後どうすればよいのでしょうか。
- 2023.07.20遺産の中に不動産があるのですが、評価額はどのように決まりますか。
- 2023.07.20遺産分割の調停はどこの裁判所でおこなうのですか。自宅に近い裁判所でできますか。
- 2023.07.20相続人の一人が認知症です。遺産分割はできますか。
- 2023.07.20茂原市で一人暮らしをしていたおばが亡くなりました。遺産として預金があるのですが、銀行によると、下ろすためには私と従兄弟全員の印鑑が必要とのことです。私と従兄弟を合わせると5人になり、最近付き合いがない方もいるので、印をもらうのが大変です。このような場合に手続してもらうことはできますか?
- 2023.07.19兄弟が亡き父の生前に多額のお金をもらっていたようですが、その分を返すように言えますか。
- 2023.07.19亡くなった父の遺言書で私の相続分がゼロとされていました。遺産からは何ももらえないのですか。